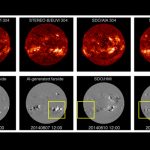写真はテクノロジーの進歩とともに発展・変化を遂げてきた。というよりも、写真を撮影するために必要な機械=カメラは「テクノロジーそのもの」だ。
写真を取り巻くテクノロジーの変化・発展は新たなカルチャーを育み、人々の世界観やモノの見方を大きく刺激してきた。目の前で起きたことを「記録」もしくは「再現」する技術、そしてまた誰も見たことがない風景を切り取る「カメラ×写真家」の視点が、社会的な価値観を前に進める上で果たしてきた役割はとても大きい。
歴史を遡れば、カメラ技術が本格的に発展を遂げ始めたのは18世紀だった。それまでの写真撮影には長時間露光や大型設備が必須だったが、1888年にはコダックが世界初のフィルムカメラを開発。それから約40年後の1925年には、ライカが35㎜フィルムを利用できるコンパクトカメラを世に送り出した。小型化したカメラは、二度の世界大戦という歴史的バックグランウドとともに、報道写真家たちの“欠かせないパートナー”となる。もしかしたら、伝説の報道写真家として名高いロバート・キャパも、カメラの小型化というテクノロジーの発展なしには伝説になりえなかったかもしれない。
写真技術の発展とコストダウンは、商業的な写真文化に大きな影響を及ぼし、企業の営利・広告活動にも欠かせないものとなっていく。世界的ファッション誌「Vogue」の表紙を見ていると、1940年代までイラストが多いが、1950年に入ると写真がその場を一気に占めはじめたことに気付く。
1975年には、米国人スティーブン・サソンによって、世界初となるデジタルカメラが開発された。当時、彼が開発したのは、100×100ピクセル、1万画素という低解像度のデジタルカメラだった。が、そのアイデアの萌芽は世界中に拡散。やがて数千万画素という高スペックが実現され、現在ではほとんどすべてのスマートフォン端末に搭載されるほどにコモディティ化した。
フィルムからデジタルへの移行、そしてスマートフォンへのカメラ搭載というパラダイムシフトは、世界中の人々を“写真家”に仕立てあげ、その作品群をデジタルスペースに共有・投稿するという流行りのカルチャーも生んだ。今日、インスタグラムやフェイスブックなどSNSを中心に、数えきれないほどのイメージが氾濫している。写真はもはや「民主化」され、一部のフォトグラファーやアーティストだけがその存在を独占するものではなくなった。
そして2018年を迎えた現在、写真およびその文化は新たなテクノロジーの登場により、さらなる変化を遂げようとしている。その新たなテクノロジーとは、多くのビジネス領域で本格的な実用化が始まりつつある「人工知能」(AI)である。
「長らく技術的な“冬の時代”を経てきた人工知能技術は、数年前に画像解析分野における劇的なブレイクスルーを達成し、改めて注目を浴びることになりました」
そう話すのは、日本のAI研究者のひとりA氏だ。A氏が端的に説明してくれたところによると、従来の画像解析技術では、対象の特徴をひとつひとつプログラムとして記述する必要があった。猫なら猫の特徴を、犬なら犬の特徴を、人間がひとつずつ丁寧に機械に教えなければならなかったという訳だ。その試みのゴールは、世界のあらやるモノ・コトを言葉に置き換える作業と同義である。素人目にもその実現不可能性は明らかだが、同分野の研究者たちは地道に関連研究を続けてきたという。
その弛まぬ努力が実ったのか、はたまた時代の偶然か、演算機械の発展やデータ量の圧倒的な増加、そしてディープラーニング(ディープニューラルネットワーク)など関連技術が出揃うことで、人間が細かく特徴をプログラムする必要がなくなる時代が到来した。機械に大量のデータを学習させさえすれば、機械自身が判断の基準を生み出し、高い精度で対象が何か見抜いたり、区別したりできるようになったのだ。その画像判断の精度が、人間の能力を超えるレベルにまで達したというのが、ここ数年間のAI分野に起こった出来事である。
「つまり、人間が持つ対象を視覚的に判断する能力が機械にも備わってきたということですが、その後もAIの成長は続いています。昨年頃からは、データを学習しながら自ら獲得した特定の基準を持って画像を新たなに再現する技術、すなわち『画像生成』においても高いパフォーマンスを発揮し始めている」(A氏)
17年10月、論文サイト「アーカイブ」(Arxiv)に驚くべき研究結果を掲載された。米カリフォルニア大学の研究チームが、人間が撮影した写真や描いた絵のスタイルを学習・模倣・応用し、自ら新たな絵を生み出す人工知能(AI)システムを開発したというのだ。
論文によれば、同システムにはふたつのAI技術が使われている。ひとつは、絵やスタイル、構造、パターンなどを分析するディープニューラルネットワークの一種「畳み込みニューラルネットワーク」(Convolutional Neural Network=以下、CNN)。ふたつめは、学習データから新たな画像を生み出す「敵対的生成ネットワーク」(Generative Adversarial Networks)だ。
研究チームはまず、ECサイト「アマゾン」で人気の高い靴、帽子、ズボンなど商品データ画像を、CNNに学習させた。その次に、GANに消費者に人気が出そうな画像イメージを生成するようにさせた。するとどうだろうか。人工知能が学習結果をアップグレードし、ユーザーにさらに好感を得られそうなイメージを次々に生成し始めたというのだ。また同研究では、ハリウッドスターたちの顔のイメージを分析した後、そのデータをベースに新たなイメージを生み出す実験も行っている。そちらでは、人間が美しいと感じる顔のイメージが、AIによって山のように新たに生み出された。
そのようなAIによる画像生成技術は、日進月歩だ。すでに多くの企業によって研究・開発、そして実用化が進められようとしている。AI用のGPU開発で世界をリードするNVIDIAの研究チームは、上記カリフォルニア大学と似たような趣旨の実験以外にも、一
定の画像データをさまざまなパターンに変える技術を公開している。例えば、「晴天の日の昼の道路の写真」があったとしよう。NVIDIAが開発しているAIシステムは、その一枚の写真データから、曇りの日、雨の日、夜間などなど、様々なレパートリーの道路イメージを作り出す。
一方、米ラトガース大学やバイドゥらの研究者チームは、対象を説明するテキストデータから画像を生成する技術の開発に成功。マイクロソフトも、文章を理解して画像を生み出す「ドローイングボット」を公開している。
その他にも、モザイク部分や見切れで隠れてしまった画像の一部復元なども、画像生成AIの進歩によって可能になってきている。そのような状況を考え併せた時、「こんな写真が見たい」と人間が言葉で伝えるだけで、人工知能が最適なイメージを生み出したり、写真を思い通りに加工してくれる日は着々と近づいているように思える。
人工知能が写真の在り方を大きく変えようとする時代を、写真のスペシャリストはどう見るか。日本を代表する写真批評家・飯沢耕太郎氏は言う。
「画像を生成する人工知能の存在は、写真やそれに関わる人々に少なくない影響を与えると思います。人工知能は予測可能なことを予測通りにやってのける能力が人間よりも高い。写真の領域で言えば、求められるイメージを忠実に再現したり、すでに流通している作風を再生産するような写真の担い手は、いずれ人工知能に取って代わられていく気がします」
人工知能はある一定の条件やルールを与えられると、人間には到底追いつけないスピードで学習していく。「ひとつのことを飽きずに繰り返し、能力や知識を高めていくマニア」(前出、A氏)のような存在だ。ルールが厳密に設定された囲碁などの分野では、もはや人間の打ち手はAIに叶わなくなった。同様に、写真分野でもそれまで人間が撮影したデータを学ばせさえすれば、ルールに則って、似たようなパターンのイメージを大量に生み出せる。そのため、ファッションや広告など、クライアントの要望に沿ってトレンドをなぞる商業写真は、いずれ人工知能に代替されていく可能性があるというのが飯沢氏の考えだ。
「ただし、アート写真の領域にまで人工知能が踏み込むのは簡単ではないと思います。予測の外側から来る偶然性を捉えて、誰も見たことのない新しいイメージを生み出すのがアート写真です。僕は『裏切る力』と呼んでいますが、優れた写真家には、偶然性を呼び込む力、モノの見方を変えてくれる力、既存のシステムやルールを変えていく力がある。それは、予測の範囲を超えないAIなど機械には、持ちえない能力だと考えています」(飯沢氏)
一方で、人工知能研究の専門家A氏からは、次のような指摘があった。
「人工知能の発展はまさに始まったばかり。アート的な画像を生み出せるか否かは、正直、今後の技術発展の経過を見守るしかないというのが感想です。個人的には『新しそうな写真』とか、見たことがない画像をAIで大量に生み出すとことはできると考えています。そういうルールを作ればよいだけですからね。ただ何を持って社会的に新しいとするか、もしくはルールを変えうるアート作品とするかは、人間の価値観によって決めるしかない。結論的に、写真アートという領域には、すべてではないにしろ、人間が担っていく部分が残っていくのではないでしょうか」
余談だが、長らく日本や世界の写真カルチャーをウォッチし続けてきた飯沢氏は、「ヴォルフガング・ティルマンス以降、世界的にモノの見方を変えてくれる新しいタイプの写真家が現れていない」と、写真アートの現状を分析する。一方で、現段階のAIが量産する「不完全な写真」が、そんな「ポスト・ティルマンスの不在=ティルマンスの呪い」(飯沢氏)を払拭すべく、写真家たちに何か知らのインスピレーションをもたらすのではないかとも期待を寄せているという。
「先日、親戚の家に最新のaiboがありました。彼が顔部分につけたモニターで勝手に撮影した写真はお世辞にも上手いとは言い難い。しかし、いろいろなものが無作為に映り込んでいたりして非常におもしろいんですよ。今AIは、より完璧な写真を生み出すために研究が進められていると思いますが、逆に不完全なAIが生み出したイメージのほうが、人間のインスピレーションを刺激してくれる材料になるかもしれません。SX-70というポラロイドカメラで新たな表現を獲得したルーカス・サマラスや、無人カメラが写した写真を作品に取り込んだルイス・ボルツのように、AIなど新たなツールが生み出すイメージをアートに昇華する能力を持った写真家の登場に期待したいです。日本では今、偶然性と思考力を持った20~30代の若手の写真家が何人か登場していますし、彼らを支えるギャラリー文化やインディペンデント系の出版文化も育ち始めている。今後、テクノロジーの発展が、写真を、また写真家をどう変えていくか楽しみです」
人工知能が人間の写真文化を席巻するか、はたまた人間が人工知能を使いこなし新たな写真文化を生み出せるかは、現段階で未知数だ。それでも、人工知能が高度な画像を量産するようになることで、社会全体に大きな影響を及ぼしていくことはほぼ間違いない。その影響の中身は、誰しもが画像を簡単に手にできるというメリット、そしてそれに負けず劣らず大きなデメリットがワンセットとなるだろう。
前述のGANで生成された写真は、もはや本物かどうか見分けがつかないほどのクオリティーを誇り始めている。例えば、そんな写真がインターネット上に大量に流通しだしたとしたらどうか。おそらく、人々は画像に写った内容を真実として捉えてしまうだろう。フェイクニュースを、完成度の高い「フェイク画像」が補強していくことだってあり得る。特定の対象者を狙い撃ちした、リベンジポルノならぬ、フェイクポルノが大量に出回る可能性も否定できない。ちなみに韓国ではすでに、GANを使ったフェイクポルノによる性的被害が問題視され始めており、今後、生成された性的な偽画像・動画を流布させた犯人を名誉棄損などだけではなく、性犯罪処罰法の範疇で裁けるよう法改正の議論が始まっているという。
AIによる写真の量産はまた、学問の世界にも大きな混乱を及ぼすと予想されている。例えば、天文学者が地道な研究の結果として撮影に成功した宇宙空間の写真、地理学者が撮影した火山の爆発シーンなどの写真なども、画像生成AIを使えば簡単に生成できてしまう。ただ人間にはその真偽を判断できない。結果、学説のねつ造や、真実が捻じ曲げられてしまうという現象も起こりうる。
「過去とは違い、現在では人工知能を容易に開発できる環境やツール、アプリケーションが整いつつあります。頭の良い高校生なら作れてしまう。AIはそんな代物になるでしょう。AIやAIが生み出した写真が氾濫する時代は、すぐそこまで迫っています。将来的に人間がいかにデメリットを回避していくか。その知恵が試されていくはずです」(前出、A氏)
最後にもう一度書きたい。写真はテクノロジーそのものだ。その進歩は、常にテクノロジーの発展とともにあった。では、写真とAIが融合する時代にはどうか。人間はAIを使って新たな写真文化を生み出すことができるのだろうか。はたまた、AIが生み出す大量のイメージに埋没し、写真の担い手としての役割を終えるのだろうか。いずれにせよ2018年を境に、写真を巡る人間と人工知能の関係はより先鋭化していくはずである。
■本原稿は月刊サイゾー6月号に掲載されたものを転載しています