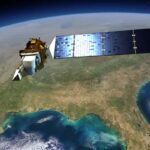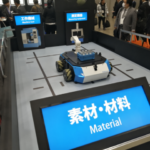人工知能(AI)やビッグデータ、ロボットを農業分野で活用する「スマート農業」が世界的に広がりつつある。
ヨーロッパでは2016年から、雑草除去と収穫量の改善プロジェクトとして、「SAGA(Swarm Robotics for Agricultural Applications)」が開始された。これは群衆ドローンに搭載されたビジョンシステムを通じて農場をチェックし、雑草の位置を正確に割り出すというもの。また群衆ドローンによって感知された雑草は、連動した芝刈りロボットが除草する。
ドローンは1.5kgの重量で、20〜30分程飛行する。広大な圃場の場合にはドローンがリレー形式で作業し、一機が業務を終えて着陸すると、代わって他のドローンが作業を続けていく仕組みとなっている。
なお同プロジェクトにおいては、すでに成果も報告されている。これまでの除草作業には農薬を広範囲に散布していたのだが、ドローンを用いることによって、雑草が集中しているエリアを優先的に除草できるようになったという。肥料や農薬の使用量を減らしてコストを削減しながら、農作業の効率アップが実現した形だ。
同プロジェクトによって、有機農場におけるドローンを使った雑草の効率的な散布や、草刈りロボットによる機械的除去が、新たな農業の可能性として証明されたのだが、考え方によっては、ドローンを各農場で購入せずとも、シェアすることができるだろう。
複数農家で共同購入してもよいが、SAGAプロジェクトを進行しているイタリア国立研究委員会(Italian National Research Council)認知科学技術研究所(Institute of Cognitive Sciences and Technologies)のヴィト・トリアンニ(Vito Trianni)博士は、「協同組合が20~30台購入し、農場の面積によって群集の大きさを調整しながら地域ごとに配置すればよいのでは」と提案している。
一方、SAGAと並行して推進されているプロジェクトに、「IoF2020(Internet of Food & Farm)」もある。こちらはヨーロッパ圏の畜産、農作物・食品の全領域を対象に、モノのインターネット(IoT)をベースとした情報ネットワークを構築し、ビックデータを収集・活用しようというプロジェクトだ。ビッグデータ収集と分析を通じて、農業を数値・データに基づいたものに変貌させることによって、農作物をはじめ、全分野の効率性が向上するものと期待されている。
例えば、センサーが内蔵された小型機器を牛の体内に挿入し、病気をはじめとした健康状態などを、個体ごとにチェックする。日々収集したデータを分析することによって、些細な変化や重篤な伝染病にも早めの対処が可能となった。また、種類分けした家畜と地域別の気候の情報をリアルタイムでクラウドに伝送し、全世界の牧場のデータとして活用する予定だ。
IOF2020プロジェクトの責任者であるジョージ・ビアス(George Beers)博士は「プロジェクトを通じて欧州全域の食品、全分野にデジタルネットワークを構築し、農業のパラダイムを新たに変化させることを目標としている」と話している。
一方、韓国では、情報通信技術(ICT)と農業の融合をスローガンとする「スマートファーム2.0」プロジェクトを、政府が推進中だ。
もともと韓国にとっての農業は、国内総生産(GDP)における割合約2.3%、農業に従事する農家人口は全体の5%となっており、主要産業とは言いがたい。しかし、韓国ではスマホ普及率が85%と言われるIT大国ならではの方法で、農業改革が進んでいる。
国内スマートファームの成功事例とされている温室栽培農家では、温室の内部と外部にバッジ水分温度測定センサーや温湿度環境センサー、co2センサー、光量センサー、気象センサーなど数多くのセンサーを設置し、栽培に最も適した環境を構築している。
農家側は情報を常にスマホやタブレットのアプリでチェックし、万が一環境が整っていなければ、アプリ内にあるボタン一つ(例えば温湿度ボタンなど)で調整が可能となっている。ソウル大学が世宗市にある農家100軒中、10軒を対象に調査した結果によると、センサー管理することによって、農産物の生産性は23%増加、一方で人件費とその他コストはそれぞれ39%と27%の削減効果を見せたという。
余談ではあるが、韓国ではゲーム会社と農家が提携し、農場ゲームアプリを提供しながら、自身がゲーム内で育てた野菜を実際に受け取ることができる面白い試みも進んでいる。ゲーム内では様々なアクションボタンが存在し(例えば「水やり」ボタンなど)、まめに作物をチェックしながら育てなければならないのだが、実際に擬似農業体験にもつながるため、話題となっている。
日本においては、農業人口の減少が深刻だ。農業構造動態調査によると、1965年の農業従事者は1151万人だったのに対し、2015年には200万人にまで減少している。また、農業従事者の高齢化も問題となっている。
日本では人手不足および高齢化対策として、農業の自動化を実現しようという動きが高まっているが、人工知能(AI)を搭載したトラクターなども登場している。
クボタが開発した「ロボットトラクター」は、GPSなどで車体の位置を計測。あらかじめ登録しておいた農地の形状や広さのデータをもとに、ハンドルや耕作装置などを自動でコントロールする。また、レーザースキャナー、超音波ソナーを装備し、圃場への侵入者や障害物に近づくと自動で停止。安全面にも配慮されている。
このトラクターを導入すれば、農地を耕したり、肥料・農薬散布が自動化できるのではと期待されている。また通常ならば、凹凸が激しかったり、雨上がりのぬかるみがあると運転が難しいが、そうした水田でも安定走行が可能なため、「農作業に慣れない人も使いこなせる農機」として、新規就農者や新米農家にも扱いやすさという利点もある。
ロボットトラクターは、2017年6月から10台ほどをモニター販売されており、農家の意見をもとに改善・本格販売が目標とされている。)
世界各国によってスマート農業のニーズは様々で、方法も多様だ。農業における先端テクノロジーの活用は、単なる収量・効率UPにとどまらず、産業そのもののビジネスモデルの拡大や新たな雇用創出の可能性も含んでいる。
Photo by Kimberly Vardeman(via flickr)