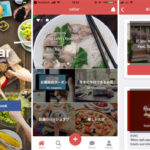「顔認証」や「声紋認証」、喜怒哀楽を判断する「表情分析」、行動の特徴を見抜く「行動検知」などなど、人間の特徴を分析するための人工知能(AI)技術の開発が、世界各地で進められている。また昨今では人間ばかりでなく、動物の生態観察・分析などにもAIが使われ始めている。なかでも、酪農・畜産分野におけるユースケースの増加は顕著だ。用途としてすでに広まっているのは、疫病の早期発見、飼育工程の効率的な管理、発情期・妊娠の早期察知、事故防止など。いずれも、IoT技術を駆使して収集した家畜のデータをAIで解析することで、人間が見落としがちな兆候やインサイトをいちはやく正確に発見しようというものである。
畜産業における人工知能活用のアイデアは、その他にも多い。例えば、中国保険大手・平安保険が養豚業者向けに展開しているサービスが興味深い。こちらは、死亡した豚がその養豚業者が所有する家畜なのか否かを、保険適応のために画像認識技術で判定する。つまり、AIを使った豚の「個体特定」である。サービスの流れとしてはまず、養豚業者が生前の画像を登録しておき、家畜が死亡した際に写真を撮影して平安保険側に送る。そして、同一の豚だと判断された場合にのみ保険金が支払われる。保険会社側にとっては調査員を派遣するコストが省ける一方、養豚業者にとっては迅速に保険金が支払われるというメリットがある。豚の顔をAIで判別するという観点には少々驚かされるが、中国の酪農・畜産業および保険業界の課題解決に根差しているという意味では、とても合理的なサービスなのかもしれない。
では日本の酪農・畜産業では、人工知能はどのように活かされてようとしているのか。報道ベースでは、マルイ農業協同組合とNECが、画像認識技術を用いた「斃(へい)死鶏発見システム」を共同開発しているという特筆すべき例がある。鶏の健康管理や鶏卵の品質管理を行う上で、死んでしまった鶏を早期に発見するという作業はとても重要だ。しかし、養鶏の現場で同作業は自動化されておらず、これまで人間のスタッフが目視で確認せざるをえなかった。規模が大きい養鶏場であればあるほどスタッフの負担は大きくなるが、両社はその負担軽減のために同ソリューションの開発に乗り出している。なお、実証実験では90%以上の高精度で斃死した鶏を発見することに成功。検知に要する時間は従来の5分の1程度だという。実用化の目標は2020年だ。
また、東京理科大学理工学部経営工学科、家畜改良センター、鹿児島大学学術研究院農水産獣医学域獣医学系、北海道立総合研究機構酪農試験場、酪農ソリューションを提供するデラバル、光学機器メーカーのトプコンは共同で、搾乳ロボットやセンシング技術、そして人工知能を併用した「畜産向け飼養管理高度化システム」の開発に乗り出している。なお、同プロジェクトが現段階で主な観察対象とするのは「乳牛」である。プロジェクトを牽引する東京理科大学の大和田勇人教授は、筆者の取材に応え次のように説明する。
「今回のプロジェクトは、牛の“内”と“外”から収集したデータをAIで解析することで、飼育や健康状態に関する高度なインサイトを見出し、酪農家や獣医などに提供することを最終目標としています。牛の“カルテ”や飼育のためのマニュアルを生み出す作業と言い換えてもよいかもしれません。解析に用いるAIはもちろんですが、牛のデータを取得するハードウェアも独自開発中です。プロジェクト期間は2016年から5年間。2年後には現場で使えるプロダクトとして完成させたいと考えています」

大和田氏が言う“内”というのは、体内のことを指す。今回のプロジェクトにはスウェーデン発の搾乳ロボットの世界的大手メーカー・デラバルも協力しているが、同社は高度な「生乳分析」の技術を保有している。乳成分からは、黄体ホルモン、乳酸脱水素酵素(LDH)、β-ヒドロキシ酪酸(BHB)などを解析することができ、その結果から、乳牛の「栄養が足りているか」「発情の時期はいつか」「乳房炎になっていないか」などを把握できるという。
「日本を含むグローバル市場では、デラバル社やレリー社製の搾乳ロボットがシェアの大半占めています。なかでも、デラバル社製の搾乳機は全自動で非常に優れた製品。レーザーで乳牛の乳房の位置を特定して自動で装着されます。牛も慣れるとロボットの柵のなかに自分から入っていくようになる。搾乳の際の個体のデータ管理もしっかりできるので、このプロジェクトではそのデータを有効活用しようと考えています」
一方で、大和田氏らは“外”からのデータを取得・解析するソリューションを開発している。こちらには、可視光およびサーモグラフィカメラや、牛に直接装着するウェアラブル端末などが含まれる。
「外からのデータ取得は、牛の体温や動き、体型などから個体の状況を把握することが目的です。いわゆる、ボディコンディションスコアの算出ですね。最終的に、牛の体外・体内のデータを包括的に取得・解析する仕組みを作りあげつつ、農場の大きさや頭数など、各現場の条件によってカスタマイズしたり、組み合わせたりして提供できるようにしていきたいと考えています」
話を聞きながら気になったのは、酪農・畜産の現場に人工知能を導入するにあたり、困難や課題はないのかという点だ。大和田氏は、「高齢化などにより従事者数や飼育されている頭数が減少傾向にある酪農・畜産業を支えるためには、自動化やスマート化が必須」と前置きしつつも、実際にAIを利活用するためには「いくつか課題がある」と話す。なかでも意外な盲点になっていると指摘するのが、「農場はインターネットにつながりにくい」という現状だ。
「日本において、牛が飼育されている酪農の現場のほとんどは中山間地。これは、においが発生するなどの条件が関係していますが、とにかく人里離れている場所が多いのです。そのため、インターネットにつながらない、もしくは仮につながったとしても接続が非常に不安定となる。この課題は、農業などともまた異なる酪農・畜産業に特有なものです」
センサーやカメラから大量のデータを取得したとしても、通信環境が盤石でなければクラウドや管制センターに安定的に送信することができない。つまり、“宝の持ち腐れ”となる。そのため大和田氏は、通信環境の限界を考慮した上で、他の技術で補っていく必要があるとも説く。
「農場の通信環境が大幅に改善するまではまだ時間がかかるでしょうから、カメラで取得したデータを端末内で処理できるエッジコンピューティングなどの技術を磨いていく必要があります。我々もすでに、通信環境が整っていない現場に対応した新しいカメラ端末の開発を始めています」
日本の「酪農・畜産×AI」というテーマについては、酪農学園大学の中田健教授にも話をお伺いすることができた。中田教授は、大阪大学産業科学研究所と共同で、乳牛の歩行パターンからひづめの病気である「蹄病」を発見するAIシステムを研究している。
「蹄病の早期発見は、あくまで酪農現場におけるAIの利活用の実験のひとつに過ぎません。日本の酪農の各現場の実情はそれぞれ差があり複雑ですし、AIをそう簡単に導入できるわけではありません。またIoTという言葉が流行していますが、そもそも、牛のデータを取る機器というのは新しく作らなくてもすでにたくさんあります。例えば、歩数を計ったり、反芻をカウントしたりする用途のものや、デラバルの生乳分析器などもそうですね。問題は、それらのデータが共有されていない、使いこなせていないことだと個人的には考えています」
中田氏によれば、日本の農家がAIを導入しづらい背景として、各家畜のデータが国によって一元管理されておらず、データの収集や利活用が各農家のモチベーションに依存している点を挙げる。また、各メーカーの製品から取得できるデータの様式もバラバラなため、整合的なデータとしてAIに学習させていくのが難しい状況なのだという。
「デンマークなどでは、牛の耳に取り付けられICチップを読み込むと、個体に紐づいた農家の情報まで表示されるよう仕組みが完成しています。データの管理を徹底しているんです。そうなると、牛それぞれの情報はもとより、その農場の問題も見えてくる。輸出をする場合には、それらのデータが自国畜産物のクリーンさをアピールする材料にもなりますし、逆にそういった管理ができていない国の畜産物の輸入をしないというバリアにもなります」
つまり、「牛のマイナンバー」に基づいてデータを徹底管理してこそ、リスクも防げ、また産業競争力も高めることができるというわけだ。さらに、整理されたデータであればAIに学習させるのも容易になる。日本全体の畜産・酪農現場でAIを利活用していくとするならば、まず何よりもデータを集める規則や紐づける手法を確立し、すでにある機器、また新しい端末からデータを共有することが第一歩と言えそうだ。
「農業の方ではすでに、国が主導したデータベース化が進み、数年後には完成していく流れです。一方で、畜産もデータを一か所に集めていく必要があります。全国的に、酪農家の5割ぐらいが加入している乳用牛群検定組合というものがあるのですが、そこでは繁殖・管理・生産経営状況を客観的に評価できるように、農家の協力を得て牛の状況を1か月に1回まとめています。現段階では、そちらが最も広範囲をカバーしているデータとなりますが、そのようなデータ収集の枠組みが広がれば、多くの現場でAIを有効活用できるベースとなっていく可能性があります」
これは酪農・畜産に限らないが、IoT技術や人工知能システムを導入していくにあたり何より重要なのは、「現場を知ること」に尽きるのかもしれない。AIはどこでも万能なわけではなく、各環境や条件にフィットしてこそ真価を発揮することができる。今後、世界の酪農・畜産業の悩みを解決するAIソリューションが登場することを期待したい。
Photo by Jenny Hill on Unsplash