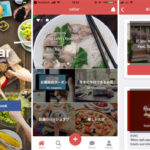東南アジアに拠点を構えるベンチャー企業への投資が加速している。一部海外メディアの報道によれば、その投資額は2013年(4億6,300万ドル)から2017年(71億6,700万ドル)までの4年間で約15倍に膨れ上がったという。一方で、スタートアップイベントのスラッシュと、シンガポールのVCであるモンクズ・ヒル・ベンチャーズの共同調査によれば、それら4年間の投資案件のうち、半数以上がシンガポールに集中しているとも報告されている。
シンガポールは2000年代半ばからスタートアップ促進策を強化。2017年には、世界のスタートアップ事情を調査する「Startup Genome」が公開した世界スタートアップエコシステム ランキング(都市別)において12位にランクインしている。なお、20位までにランクインしているアジアの都市は、北京(4位)、上海(8位)、バンガロール(20位)など(ランキングには調査する言語上の問題から日本は含まれていない)。ランキングはファンディングだけでなく、企業のパフォーマンスやタレント、マーケットリーチなどを総合的に分析したものとなっており、その結果からはシンガポールがアジアを代表するベンチャー拠点の一角となっている現状がさらに鮮明に浮かび上がってくる。
シンガポールに本拠地を置き、「研究と実践」を通じて超長期の産業創造に取り組むベンチャービルダーREAPRAの投資チームを率いるプリシラ・ハン氏は、明日の成功を夢見る起業家たちの活動は活発だと現地の状況を説明する。
「弊社はシンガポールでそれなりに認知が高いという理由もあるのですが、たくさんの問い合わせをいただいています。毎日、2~3件は常に新しい案件をフォローしている状況です。私が同社に来て1年半の間にレビュー(検証)した数だけでも約400件になります」
シンガポールのベンチャーエコシステムが強化された背景には、政府の大規模なテコ入れがある。2014年、シンガポール政府はさらに豊かな生活、生産性向上、新たな仕事・雇用を創出できる技術力を持った国を意味する「スマートネーション」という構想を打ち出し、その後、本格的なベンチャー支援に乗り出している。特定技術の研究開発に190億ドルを投資する「RIE2020計画」や「StartupSG」がその例だ。また政府所有データの一般共有や、国内各地域に先端技術の実験場をつくるなどの施策も展開している。
その他にも、シンガポール政府のベンチャー企業支援の全体像は多岐に渡っており、ベンチャー側は資金、技術確保、育成プログラムなどさまざまなバックアップを受けられるようになっている。一方で、エンジェル投資家に認定されると投資2年後に投資額の50%の税金控除を受けられる「Angel Investors Tax Deduction(AITD)」など、投資家を優遇する制度も充実している。

旺盛な産学官連携も、スタートアップエコシステムを支える要因のひとつだ。シンガポール国立大学やシンガポールメディア開発庁などが共同運営する「Plug-in@Blk71」のようなインキュベーション施設、またシンガポール金融管理局(MAS)とシンガポール銀行連盟(ABS)が共同で主催する「シンガポール・フィンテック・フェスティバル」などのテックイベントはその一例となる。
ただ起業家たちと現場で向き合う前出のハン氏は、シンガポールのスタートアップエコシステムにも課題があると話す。そのうちのひとつが、起業家たちが持つイノベーションやビジネスに対するスタンスの問題だ。
「シンガポールでは、多くの起業家が早く結果を得ようと焦っているようにも思います。というのも、各起業家がそれぞれのゴールに到達するのには、100通り以上のやり方があると私は考えています。そのなかには時間がかかるやり方も、短期間で成果を収めようとするやり方もありますが、後者を選びたがる起業家が多い。しかしながら、彼らの事業領域やビジネスモデルにおいて成功を収めるには、その方法が必ずしも適していない場合もあります。急ぎすぎるがゆえに企業が短命で終わってしまうというケースが非常に多いのです。特にミレニアル世代の起業家は、お金や結果を急ぎすぎることで損をしてしまっていることが多いように見受けられます」
順風満帆に見えるシンガポールのベンチャー事情。日本でもシンガポールをフィーチャーする報道は多いが、実際にビジネスやイノベーションを創出するのは人間だ。ハン氏はシンガポールを担う次世代の起業家たちにとって、「忍耐力」はひとつの課題になると考えているという。
「シンガポールに限って言えば、若い世代はとても恵まれた環境で育っています。人生の大半が安定していて、特に大きな問題を抱えたことがありません。つまり、すべてが簡単に手に入ると思う傾向が強いのです。この考え方は、将来的にシンガポールに困難をもたらしうるのではないかと個人的に思っています」
社会に課題が多く山積しているからこそ、東南アジアベンチャーには大きな可能性が秘められている。しかしながら、課題を感じ取る能力が起業家の中から失われてしまえばどうか。ハン氏の指摘からは、人材の共感力というフィルターを通じたシンガポールベンチャーエコシステムの課題が透けて見えてくる。
シンガポールのベンチャー事情をよく知るハン氏は、日本の状況をどう見るのか。日本経済を取り巻く話題はネガティブなものが多いが、ハン氏の意見は逆だ。
「日本は東南アジアとは異なり、色々な社会課題に直面している課題先進国。しかし、他国の人々は、日本人自身が日本を見るよりも日本をポジティブに見ています。少なくとも、私や私の周囲の人たちは、日本のマーケットがこのまま衰退していくとは考えていません。日本は魅力的な場所が多く、食事もおいしい。人々もとてもユニークです」
日本は課題先進国であるからこそ、さまざまなビジネスチャンスがあるはずだとハン氏は言う。一方で、実際に日本人と接しながら共通した印象を受けるとも。それは「将来に対して悲観的」ということだ。気持ちの問題と言ってしまえばそれまでだろう。しかし、モノゴトの成否は“気持ち”や“心の持ちよう”に左右されることが多い。日本、もしくは世界にはいくらでもチャンスは転がっているのに、多くの日本人は将来を憂慮するあまり自信がないようにも映る。ハン氏はそのことをとても不思議に感じるそうだ。
「日本の方々と話すと、自分の将来を心配している方が多いという印象を受けます。彼らにはガラスの天井が存在していて、みな『日本から出たい』と言います。なぜか自分に限界を感じていて、自己評価も低いことがとても奇妙に感じられます。しかも、まだ若い人たちばかりなのに。以前に日本の学生をシンガポールに招いてスタートアップについて学ぶ機会を提供した時、30人くらいの学生に『将来、起業家になりたい人は?』と聞くと、1人しか手を挙げなかったことがあります。『両親に反対される』『資金を得ることができない』などが、その理由でした。もちろん起業が最良の選択というわけではありません。それでも、卒業前に自分の限界を決めてしまっている傾向があり、非常に残念なことだと感じました」

ハン氏は少子高齢化など先進国ならではの課題が山積みである日本だからこそ、そのアドバンテージを活かせる分野もあるとする。例えば、介護や福祉だ。今後、他国には真似できないクオリティのサービスを、外国人向けに開放していくのもひとつのビジネスになるのではないかと言う。
ハン氏によれば、シンガポールでは少子化や価値観の変化により、子どもが老親を介護するという考え方が薄れてきている一方で、老人福祉施設は低所得者向けばかりで、富裕層や中間層向けの施設もない。距離的に近い他の東南アジア各国では高齢者施設産業をつくろうという動きはあるが、スキルやノウハウがなく困難に陥っている。一方、日本には関連産業のノウハウが蓄積しており、そんな日本で老後の生活を営みたいというシンガポール人は決して少なくないというのだ。しかも日本の場合、地方では安価な土地がたくさんある。言語などをサポートできる外国人向け福祉・介護施設というのもひとつのアイデアになるのではないか。
こうしたアイデアはほんの一例に過ぎない。日本社会と海外各国の強みや社会課題を結び付ければ、新しいアイデアはたくさん湧いてこよう。多くの外国人がすでに日本を訪れ、その社会や文化を理解し始めている現在、現実的なアイデアが増え続けるだろうとハン氏は言う。
「多くの日本人が日本を去りたいと考えている一方で、より多くの外国人が日本に行きたいと考えています。日本はとても長い間、独自の文化や作法を守ってきました。そのため、実際に人々の習慣が変化するのには、諸外国より時間がかかるかもしれません。しかし、多くの外国人が日本を好きな理由は、日本がその独自の文化や習慣を守ってきたからこそ。伝統と変化の調和は簡単ではありませんが、外国人の視点から見た時、日本が持つ可能性はビジネスや社会構造、文化的側面などあらゆる観点からとても大きいと感じています」
急成長を遂げるシンガポールのベンチャーエコシステムの中においても、課題や問題はある。一方、経済規模のシュリンクが進む日本においても、ベンチャーが大きな成功を勝ち取れるチャンスは決して少なくない。ハン氏の指摘からは、環境や状況を言い訳にせず、社会やグローバル市場で何が必要とされているかを真摯に考え続けたプレイヤーにのみ道が拓けるという真理が浮かび上がってくるようだ。
■写真・取材協力:河原良治・天沢燎