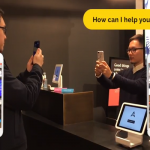「同室感」もしくは「超臨場感」というテクノロジー関連のキーワードがある。これは、別の場所にいる人々が、「あたかも同じ空間にいるかのような感覚」を共有するための技術およびシステムを総称する言葉だ。
新型コロナウィルスの影響で外出が制限され、多くの人がZoomなどリモートコミュニケーションに触れる機会が増えている。メールやチャット以上の意外な便利さに、対面であることが必須だとは感じなくなったり、もしくはミーティングのための時間の使い方などを見直す人々も増え始めていることだろう。
一方で、リモートコミュニケーションツールの“限界”を感じている人も少なからずいるはずである。確かに用は足りている。が、対面コミュニケーションと比較すると何かが欠落しているかもしれないという“違和感”がそこにある。
違和感の原因を探っていくと、まず通信環境の問題がある。各人が置かれた通信環境は千差万別だ。場合によっては、音声が聞き取りにくかったり、相手の表情がよく見えなかったり、もしくは通信自体が途切れてしまうこともある。人間は対面でコミュニケーションを取る際、多くの情報を絶え間なく収集・処理している。しかし通信状況が悪いと、ところどころその情報が欠落してしまい、インプットが断片化してしまう。
とあるベンチャー企業家からはこんな話もあった。
「最近、ベンチャー界隈では、資金調達に非常に苦労していると言います。もちろん、経済が止まってしまって、資金自体の流動性が低いという理由はあります。ただそれだけではありません。プロジェクトやサービスを売り込む時に、リモートコミュニケーションツールだといまいち熱が伝わらない。結果、出資先の反応が鈍いというのです」
この「熱が伝わらない」という課題はベンチャー界隈以外にも偏在しているはずで、現在のリモートコミュニケーションツールが、通信という領域以外にも限界を抱えているということを紐解く糸口になるかもしれない。
人間は対面コミュニケーションの際、視覚、聴覚以外にも、触覚や嗅覚などさまざまな感覚を複合的に組み合わせて、対象の人となりや現場の空気を把握する。しかし、現在のリモートコミュニケーションが繋ぐことができるのは、視覚と聴覚だけ。しかも、そのふたつも制限される。例えば、対面では部屋の隅から隅まで見えるが、オンラインだとウェブカメラの画角など一部の視界しか捉えることができない。ここでは通信環境という要因以外によって、情報の欠落という問題が生じている。
そんな問題を解決しようとするのが、「同室感」もしくは「超臨場感」という分野の研究だ。
例えば日本では、大阪大学の中西研究室が、ディスプレイとロボットハンドを連動させて、「デジタル世界に触れる」もしくは「映像から身体が出現する」というコンセプトを実現しようとしている。リモートコミュニケーションに触覚を取り入れることで、「ソーシャルテレプレゼンス」(実際には離れた場所にいる他者とあたかも同じ場所 にいるかのような感覚になることができる現象)を強化しようという試みだ。
中西研究室のHPには「今の技術に縛られたテレビ会議はリアルに程遠い」という問題意識とともに、「現状の技術や既成概念に縛られない自由な発想があれば、まだまだソーシャルテレプレゼンスの可能性は広がる」という指摘がある。
「同室感」や「超臨場感」を高めうる技術として、その他に注目されているものにAR/VRがある。こちらは限定された視覚情報を補完するという意味合いが強く、大学や企業など多くのプレイヤーが研究に参戦している。
昨今、フィジカルな世界(リアル世界)をデジタルデータに置き換え有効活用しようというテクノロジーが相次いで登場している。IoTやデジタルツイン、人工知能(AI)などもその範疇となるだろう。一方で、「同室感」や「超臨場感」に関する課題設定は逆。デジタル情報をフィジカルな世界に置き換えようというものである。その研究が進めば、デジタルコミュニケーションの円滑化だけでなく、デジタルキャラクターと触れることができる世の中が来るかもしれない。実際に同研究分野では、「プロジェクト・タッチ」というVtuberに触れたいを実現するプロジェクトも始動しているという。
対面かつフィジカルなコミュニケーションの強度が100だとしたら、リモート技術はどこまでそこに近づくことができるのか。あるいは、人間の脳に直接作用するような全く新しい技術が登場し、対面と遜色ないかそれ以上のコミュニケーションが可能になる日がくるのだろうか。リアルとデジタルの世界を結び、超越するテクノロジーの登場に期待したい。
Photo by Fares Hamouche on Unsplash



![【ルポ】急速発展する中国最貧エリア・貴州省[vol.2]...深セン並に先端サービスを実装](https://roboteer-tokyo.com/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180307_142156-768x576-150x150.jpg)