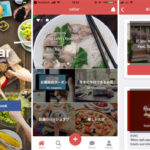様々な分野で活用が期待されるドローン。なかでも最近、注目が集まるがエンターテインメントおよび広告面での活用だ。複数のドローンが連携して一糸乱れぬ動きを見せたり、光を放ちながら飛びまわる姿は、独特な世界観を演出し人々を魅了してやまない。今回、ロボティア編集部では、ドローンや先端技術を使った作品をてがけ、世界的に活躍する日本の企業ライゾマティクス社を訪問。取締役・石橋素氏(写真中央、Images by Carmen Kam)に話をお伺いした。
―以下、インタビュー(太字はインタビュアー質問)
―ライゾマティクスでは、先端技術を取り入れたプロジェクトや作品を多く手掛けてらっしゃいます。方々から反響が多いかと思うのですが、本来はどのような事業を展開されているのでしょうか。事業ポートフォリオについて教えてください。
ライゾマティクスは広告、エンターテイメント、アート分野を主な事業ポートフォリオとしています。最近では、クライアント企業が新製品を発案した際にデモ機やプロトタイプをともに開発する業務や、ブランディング含めたR&D開発、コンサルティングなどにも従事させていただいています。
なお、会社設立は2006年です。当時、ウェブ関連事業に携わるチームと、メディアアートを展開していたチームが合流することで現在の会社の形となり、社員数は40名弱となっています。業界動向としては、年々ウェブ単体の仕事が減少傾向にある。そのため弊社では3~4年前から、インスタレーションなど、ユーザーが直接体験できる装置を駆使して、それを動画で撮影、広告に取り込むような事業も展開してきました。
―ライゾマティクスリサーチがマルコ・テンペスト氏とコラボレーションした「ドローン・マジック」は、日本国内および海外から多くの注目、反響を集めています。どういう経緯で実現したのでしょうか。また、2014年末に紅白歌合戦に登場したPerfume(Perfume)の舞台でもドローン関連の演出のテクニカルサポートを担当していらっしゃいますが、ふたつのプロジェクトに共通点や違いはあるのでしょうか。
まず時期としては、Perfumeさんの舞台が先になります。当時すでにドローンの機体やシステムは実験を繰り返していて、どのような機会に発表するかを探っていました。
Perfumeさんが紅白歌合戦で披露した「ClingCling」という楽曲は、PVにアジアテイストの世界観や提灯を取り入れていました。そのため、紅白歌合戦の際に演出家の方々と相談して、ドローンでふわふわ浮かぶ提灯を再現するという方向に。曲の雰囲気にも合うし、技術的にもチャレンジングだということで“GOサイン”がでました。
テクノイリュージョニストのマルコ・テンペスト氏とは以前から知り合いで、一緒に作品を作りたいと話していました。紅白後に、僕たちの方でドローンとダンサーパフォーマンスを組み合わせた作品「24 drones」を発表したのですが、それを見たマルコ氏と計画が進み、「ドローン・マジック」が実現しています。作品を公開したのは半年ほど前になりますが、準備はその約1年前から続けてきました。
なお、紅白歌合戦と24 dronesで使用した機体は、同じものになります。ただ、紅白歌合戦の際は機体の下に提灯をつけて飛ばしていて、24 dronesでは機体の上にライトを搭載しています。

―ドローンの機体は自社で製作しているのでしょうか
パーツなどはそれぞれ買って組み合わせていますが、基本的に自社で製作しています。もともと、ドローンを使ったプロジェクトを構想する段階で、ダンサーと共演するということを決めていました。そのため、台数が多くなることや、接触などのアクシデントも想定していて、なるべく小さくて、軽量なものを作るように心掛けてきました。
ドローンやそのシステムに関しては、試行錯誤や改良を2~3年ほど続け、機体も5~6種類製作しています。舞台やパフォーマンスは、内容や環境が都度異なりますので、その時々に合わせてカスタマイズして作りこんでいます。現在、カスタマイズする場合にパーツを集めやすい環境、組み合わせが整いつつあり、フレームだけ自分たちで設計して3Dプリンタで出力するような形です。細かなカスタマイズができるのは、ドローンの利点のひとつになるのではないでしょうか。

―舞台にドローンを導入する際は、その経路や動きなどを事前にプログラムして、完全に自立飛行させるのでしょうか。もしくは、オペレータがマニュアル操作するのでしょうか。
技術的にはどちらも対応可能です。が、実際には事前にプログラミングした自律飛行が多いです。そのドローンのアクションに合わせて、アーティスト側が動きを合わせる形ですね。特に楽曲が決まっている場合は、そちらのパターンかなと。「MAYA(3次元コンピュータグラフィックスソフトウェア)」などで動きを作って、その座標データをドローンに送信したりなど、いくつかの方法を駆使しています。一方で、人物の動きをリアルタイムに解析して、その動きにドローンを合わせるという手法も使えます。

―最近、エンターテインメントと広告、また先端技術やアートの領域が曖昧になっている、もしくは近づいてきているという印象があるのですが、その点についてはどのような考えをお持ちですか。
僕たちとしては、これまでやってきたことと、最近の動向が異なるという認識はあまりありません。エンターテイメントや広告分野では、クライアント側が実現したいこと、もしくは何かを達成したいという意向がまずあって、僕たちはその課題をどうクリアするか、叶えるかという点に徹しています。
一方、アートは僕たちの側が世の中に発信したい内容を込めるようにしています。アート分野で新しい表現に挑戦し、それを見たクライアントの要求に沿って内容を発展させ、エンターテイメントや広告分野に活かしていく。ライゾマティクスの特徴は、その両輪があることだと思います。
―ドローンに関連するプロジェクトを進める上で、刺激を受けた人物や団体はありますか
広告サービス系ではないですが、スイス・チューリッヒ工科大学のラファエル・ダンドレア氏率いる研究チームの活動は、とても刺激になります。ドローンに関しては、非常に先端的な研究をしていらっしゃる。ちなみに、ドローン関連のプロジェクトやイベントのオファーをいただくのは、海外企業や団体が多いです。まだ世界を探しても、同様の技術を持った企業は数社しかなく重宝してもらっています。
―ドローン以外の先端技術を駆使したプロジェクトについてもお聞かせ下さい
先日、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)を取り入れたプロジェクトも発表しました。「border」というパフォーマンスです。これは、ヘッドマウントを装着してもらった10人のお客さんにパーソナルモビリティに乗ってもらって、会場には白い箱を5つを置き、周囲ではダンサーがパフォーマンスを行います。
ヘッドマウントにはミックスド・リアリティ、つまり実写とCGが組み合わされた映像が流れます。参加している皆さんは、現実と仮想現実の境界を体験することができます。パーソナルモビリティはWHILL社にお借りして、位置や動きは事前にプログラミング、制御しています。そのほかの先端技術を使ったプロジェクトも、常にテストや開発中です。

―広告と先端技術の未来についてはどのような私見をお持ちですか
今後、各企業が開発する技術・製品は、生活など実用的な面でどんどん高性能になっていくと思います。ただ、広告表現として、ドローン、AR、VR、またそれに次ぐトレンド技術が頻繁に使用されるようになるかと言われれば、僕個人としては少し懐疑的な面もあります。というのも、本質的な部分と少しずれている感が否めないからです。
例えば、とある企業が開発した新商品があり、その商品とAIはまったく関係ないとします。その時に、広告としてAIを使った表現をするというようなケースは、これまでにもありました。しかし、それはあくまで広告での見せ方の話にとどまりますし、AIの表面的な使い方に過ぎない。企業側としては、それらの技術を取り入れて、サービスもしくは製品を良くしていく方が正しいと感じていると思います。僕個人としても、先端技術を導入した広告表現は、それら技術の“表面”だと思っていて、もう少し深い部分で活用する術を企業とともに模索する方が正しいと思っています。
―人工知能やドローンなど、テクノロジー発展については、危険視したり、ネガティブな論調もあります。そこについてはどう思われますか。
僕たちとしては基本的に楽観的な姿勢で、より楽しく、より驚きがあることを仕掛けたり、技術の良い側面を伝えていきたいと考えています。
実は、ドローンのパフォーマンスを準備しはじめた当初、ダンサーの皆さんが怖くて踊れなかったということがありました。あれだけブンブンと周囲にドローンがたくさん飛んでいるので、無理もありませんよね(笑)。ただ、練習を繰り返していくうちに、ドローンがどういうもので、どういう挙動で動くのか分かってくる。最終的に接することができるようになり、新しい表現を獲得するという結果にいたりました。
それは、人間の適応力の高さを示すエピソードだと思いますし、ダンサーさんに限った話ではないと思います。人間は、得体が知れないものでもやがて理解できるようになるし、それを上手く使いこなせば、それまでなかった“豊かさ”が生まれるのではないでしょうか。