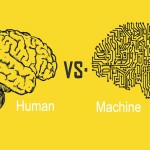「人工知能100年研究(One Hundred Year Study on Artificial Intelligence=AI100)」というプロジェクトがある。今後100年に渡り、人工知能技術がどのように発展し、社会にどのような影響を与えるか、継続的に観測・分析するというプロジェクトだ。
今回、ここに参加している17人の専門家が、プロジェクト発足後2年の時を経て、初のレポートを提出した。レポート名は「2030年の人工知能と生活(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LIFE IN 2030)」。2030年の頃の近未来に、人工知能技術が北米に住む人々の生活をどのように変化させるか分析したものとなる。
約50ページの同レポートは、8つの分野を分析。その結果を報告している。もっとも、興味深いのは「人工知能と輸送手段」の分野だ。レポートは、今後、自律走行車および輸送手段がすぐに普及し、ほとんどの人々はそれらを通じて“物理的形を持った人工知能”を初めて経験することになるだろうと予想している。加えて、その経験が人工知能の認識を左右することになろうともいう。
レポートは、人間よりも優れた運転能力を備える自律走行車が登場すれば、人々は車を所有しなくなり、あえてオフィスに近いところに住まいを構えなくなるとする。また、運転することがなくなるので、人間は一日50分の運転時間(米国の都市生活を基準)を自分の時間として有効活用できるようになるとも指摘した。
加えて、自律走行する車やトラック、ドローン宅配便などが、通勤や業務、ショッピングの方法を大きく変えると強調。フライングカーおよび、パーソナルロボットの登場も期待した。一方、陸・海・空をまたぐ、ドローンのような全く異なる交通手段の出現には否定的だ。
ホームサービス分野では、荷物の運搬、オフィスの清掃、セキュリティを担当するロボットが登場すると予見している。 2025年頃には、ロボットアーム型のヘルパーが、家庭にも姿を現すそうだ。
ヘルスケア分野では、人工知能をベースにした製品やサービスが次々と登場。数年以内に、数百万人の生活の質を改善させるだろうとしている。続いて、教育分野では人工知能によるパーソナライズ教育が普及。オンライン教育が、正規の教育課程にも導入されると予想する。
公共の安全、またセキュリティ分野も人工知能の活躍が期待される分野だが、レポートは、クレジットカード詐欺のようなホワイトカラー犯罪の追跡に高い成果を残すと予想する。2030年には、監視用カメラとドローン、人工知能による予測を土台とした、治安維持活動への依存度が大きく高まるだろうという可能性も示唆。現在、人工知能による治安維持活動は、まったく罪のない市民を予備犯罪者として分析対象にしてしまう可能性も孕む。が、うまく活用されれば犯罪を回避することに繋がるとする。
エンターテイメント分野では、人工知能により参加型、個人型的、双方向型のメディアが全盛を迎えるだろうとする。また、さまざまなツールやアプリが、高品質なコンテンツを簡単に作れるように手助けするとも。
雇用分野では、人工知能が近い将来に「雇用」というよりも「仕事」を代替する可能性が高いと予想した。レポートは、人工知能がどのような仕事をなくすか比較的明らかだが、一方で新しい雇用を予想するのが難しいとしている。
人間の労働の割合が低下するに応じて、労働に対する対価(反対給付)だけでは、適切な生活を維持しにくくなる。これは、経済的な対応よりも政治的な対応が必要な問題だ。レポートは、短期的に「再教育と訓練」を、長期的には「基本的な所得保障などの社会的なセーフティーネット」を進化させていくことを提案している。
人工知能が研究・開発、そして普及が成功するか否かは、人間の生活にどのように貢献するかにかかっている。また、人間の生活や社会をより豊かにする方向に人工知能をどのようにコントロールしていくか、議論が急務だとレポートは強調する。
レポート自体は、人工知能に関して非常に友好的かつ楽天的である。「人間の仕事が奪われる」といようなディストピア的な未来を懸念する人々に対し、「自ら長期的な目標・目的を持ち動作するマシンはまだ開発されていない。近い将来に開発されることもない。代わりに、2030年までに社会と経済に有用な使い道が増えるだろう」と説明する。
一方で、人工知能が人間の労働を拡張・代替することで、これまでの社会の枠組みが変化していくことに同意。その点について、バランスをとることが非常に重要だと指摘する。
レポートは結論的に、人工知能への恐怖と猜疑心が蔓延すると、その発展の足を引っ張ることになりかねないし、最終的には、人工知能技術の安全性と信頼性を害する結果になるだろうとする。もはや人工知能開発はすでに規制できない段階に入っており、それを認めた上で、議論や法整備、教育を進めるべきという判断があるのかもしれない。なお研究チームは、今後5年ごとに調査報告書を出す計画だ。