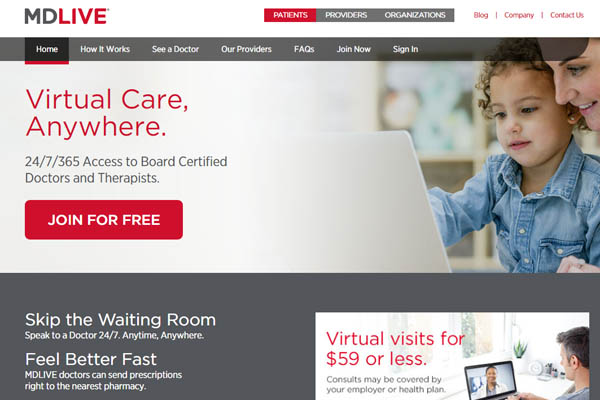8月下旬から9月上旬の間、ハリケーン「ハービー(Harvey)」「イルマ(Irma)」が立て続けに米南部を襲った。これらのハリケーンの規模は2005年のハリケーン「カトリーナ」に匹敵するほどの猛威を振るい、テキサス州やルイジアナ州、フロリダ州に壊滅的被害をもたらした。そこで、大洪水により孤立状態となった住民を救済する手段として注目を集めたのが「遠隔診療(オンライン診療)」である。
ハリケーンで被災した住民への遠隔医療サービスの提供に協力したのは、スマートフォンのビデオ通話を活用した遠隔診療サービスを強みとするエムディライブ社(MDLive)、ドクター・オンデマンド社(Doctor on Demand)、アメリカン・ウェル(American Well)などだ。ハリケーン襲撃日より数日間、遠隔診療サービスを無料で提供し、ハリケーン被害に遭った住民をサポートした。
災害発生後の1週間は病気のケアが制限されがちである。特に糖尿病などの慢性的な病気を患っている場合には、治療の中断が命取りになることがある。また、下水が逆流し、地上が汚水で溢れかえれば、感染症のリスクも避けられない。
テキサス州は米国50州の中で遠隔診療の推進に対して最も消極的であった。今年の初め、ようやく遠隔診療の普及を後押しする新法案を可決し、現在に至る。
日本国内でもスタートアップを中心に、遠隔診療プラットフォームを提供する企業が急増している。政府は「未来投資戦略2017」において、IoTやビッグデータ、人工知能、ロボット、シェアリングエコノミーなどを通じた第4次産業革命を中長期的な成長の原動力と位置づけるなかで、遠隔診療の推進も視野に入れている。スマートフォンのチャット機能を活用した遠隔診療の実証実験を進めるなど、官民一体となり、遠隔診療の普及に努めている最中だ。
一方、南オーストラリア大学の研究グループでは、自然災害や紛争地帯での活用を想定したドローンの開発が進められている。同大学で開発中のドローンは患者の心拍数や呼吸速度などを遠隔で測定する仕組みとなっており、これは世界初の試みであるという。研究成果については、2017年8月8日、医用生体工学専門誌『バイオメディカル・エンジニアリング・オンライン(Biomedical Engineering Online)』の電子版に公開された。
ドローンはカメラや画像処理系アルゴリズムを標準装備しており、人間の顔や首を検出し、静止状態でなくても心臓の鼓動や呼吸数を正確に数値化。そのうえ、数名単位での測定・モニタリングを実現する。例えば交通事故で負傷後、救急車が来るまでの緊急用処置としても重宝しそうだ。
アフリカなどの発展途上国では、生後すぐに感染症に罹り、そのまま命を落としていく新ケースは後を絶たない。新生児向けのバイタルサイン計測用非接触型センターの開発を目論むなかで生み出されたのが今回のドローンであると英BBCは報じた。
2歳から40歳までの15名の被験者を対象に行った実証実験では、3メートル離れた距離からの測定に成功。ゆくゆくは50メートルや500メートル頭上でも使えるようになる。自然災害などにより孤立した被災者に対する新たな救済手段として期待が持たれる。
ドローンで被災者を発見し、バイタルサインを計測しながら、必要に応じて遠隔で医師による助言を得る。もちろんプライバシーや倫理的な問題は避けられないが、地震や豪雨などの自然災害と隣り合わせの日本において、ドローンと遠隔診療を組み合わせた医療サービスが定着する日は意外と近いのかもしれない。
Photo by MD Live