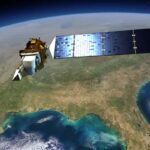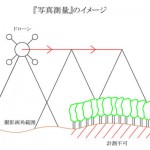日本のドローンの歴史を語る上で欠かせない企業がある。二輪メーカーとして有名なヤマハ発動機である。ヤマハ発動機は、1983年から商業用の農業用小型無人飛行機の研究に着手。30年近く開発を続けてきた企業であり、同分野の世界市場においてトップの実績と技術を誇っている。
2015年5月5日、そのヤマハ発動機の技術が世界を驚かせた。
米連邦航空局(FAA)が、ヤマハ発動機が開発した農薬散布用小型無人飛行機「RMAX」に対し、『sectoin333』を適用したのだ。この『sectoin333』の正式な表題は「SPECIAL RULES FOR CERTAIN UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS」。すなわち無人機運用における米航空法の例外措置を定めたものだ。また米国内における無人機の商用利用にあたり、機体の安全性や性能、合法性を保証するガイドラインという性格がある。分かりやすく言えば、米国で無人機を商用利用して良いという正式な認可である。
2015年5月28日現在、『sectoin333』は455の申請に対して適用されているが、農薬散布用小型無人飛行機として適用が決まったのは、今回がはじめてだという。これは、ヤマハ製の機体が米国の厳しい審査を通過し、世界のドローンに先駆けて、農業分野における小型無人飛行機の実用化の道を開いたことを意味する。 今回のFAAの決定には、米国のドローン関係者も大きな期待を寄せている。
ヤマハ発動機の認可を後押ししてきた米国際無人機協会(AUVSI)代表のブライアン・ウィン氏は、米メディアに向け「今回のFAAの適用は、無人機が米国の産業にもたらすであろう利益を気付かせる上で重要な一歩になる」と指摘。今後、「農業分野における、無人機の潜在力に注目が集まるだろう」ともコメントを残した。米国初認可となったヤマハの農薬散布無人飛行機。その開発の裏側には、どのようなストーリーがあったのだろうか。その歴史と困難、海外への普及事情や、今後の見通しなどを含め、開発担当者に直接聞いてみることにした。

取材場所となったのは、静岡県磐田市にあるヤマハ・コミュニケーションプラザ。ちなみに、ヤマハでは自社で開発した機体については、ドローンという呼称では呼んでおらず、産業用無人ヘリコプターという名称で統一している。
「最近、ドローン関連の取材で着ていただくことが増えて非常にありがたいんですが……。なにせドローンという言葉は軍用標的機のイメージが強いので」
ヤマハ発動機UMS事業推進部開発部長と、日本産業用無人航空機協会理事を兼任する坂本修氏は、取材の冒頭で定義の違いについて説明してくれた。坂本氏は小型無人機開発に長らく尽力してきたエキスパートである。
「弊社製品とドローンとの違いを説明するのであれば、我々が開発しているのはシングルローター式だということですね。シングルローターヘリを開発するためには、飛ぶ原理や機体全体のことを理解する必要がある。例えば、航空力学とか機械力学とかですね。比べて、ドローンやマルチコプターは、モーターやプロペラ、制御ソフトさえあれば、飛行に関する知識がかなり少なくても飛ばすことができます」
また、ヤマハ発動機が開発しているシングルローター無人機は、一般のドローンに比べてサイズが大きい。フェーザーという機体は全長が3.6メートルで、積載重量は30㎏。連続飛行時間は1時間。動力はガソリンエンジンだ。
「ドローンのように電動だと、さすがにそこまでは難しい」
なお、ドローンのもっとも大きな特徴のひとつは自律飛行だと言われているが、ヤマハのシングルローターヘリも自律飛行が可能な段階にあるという。製品の差を一通り説明してもらった後、早速本題に入る。ヤマハ発動機は、なぜ無人飛行の分野に進出したのだろうか。坂本氏は言う。
「もともと、この農薬散布用無人機の開発は、1980年に農林水産省が打ち出した政府のプロジェクトだったんですよ。当時、有人ヘリコプターで農薬散布をしていたのですが、ちょうど減反政策や市街地の拡大していた時期でした。いずれ有人ヘリは使えなくなるだろうということで、小型無人機開発の議論が始まったんです」
また当時の日本では少子化と高齢化、若者の農業離れによる過疎化が問題として浮上しつつあった。政府の立場からすると、農作業や米作りに支障が出ることは避けたい。そこで、外郭団体である農林水産航空協会に研究助成金を出して、有人航空機の補完用として、農薬散布用の無人航空機開発に乗り出したというわけである。

当初、開発の先陣を切っていたのは神戸機工。二重反転式ヘリが仕様として策定され、研究開発がはじまった。が、目に見える成果を得ることができず。その後、ヤマハが政府に開発委託を受け開発に着手したそうだ。ヤマハ発動機は、1987年に世界初の産業用無人ヘリ「R50」の開発に成功し、翌年1988年から本格的に販売を開始している。
「展示してあったフェーザーをご覧になりましたか?デザインがバイクみたいですよね。ヤマハで作った無人機がなぜああいうデザインかというと、新しく農業を担う若者に誇りを持って欲しかったからなんです。最新技術を駆使した無人飛行機を飛ばして農作業をする。その飛んでいる機体もかっこいいとなれば、農業のイメージも変わると考えました」
坂本氏の話を非常に聞いていて、非常に興味深かった点がふたつある。ひとつは、当時の国際社会では、日本政府のように農業に無人機を導入しようとした例が見当たらなかったこと。そしてもうひとつが、日本国内において、産業用無人機の需要がなかったという点である。

「販売当初はまったく需要がありませんでした(笑)。それにはいくつか理由がある。そもそも、農業分野はリスクヘッジに敏感です。なにせ、失敗すると食べる物ができなくなるわけですから。また農薬散布となると、防除効果や残留農薬の影響が消費者に直結する。無人機が食の安全を確保できるかどうか、業界が非常に懐疑的だったんですね。現在、ドローンの安全性が問われていますが、農薬散布用無人機の分野では35年前から、すでにその議論がはじまっていた」
例えば、農薬散布用無人機を実用化するとなると、少なくとも地上機で散布したものと同等の防除効果が得られなければならない。また、残留農薬の問題があるため、農薬と作物、機体の組み合わせに不都合がないか徹底的に調べる。この事情はどの国でもほとんど同じなのだが、日本の場合特に厳しいという。ひとつの農薬につき、最低2年くらいかけてテストが行われるそうだ。

「米国のワイナリーだと年間10回くらい散布する。その都度、農薬が違いますし、ワイナリーによっても異なる。日本ほど厳しくはありませんが、それぞれ効果があるのか試験工場でテストして実用化まで持って行くのです。もちろん、新しい農薬が開発されれば、その都度テストします。それで改良が必要となったら、農薬を改良したり、機体を改良しながら、組み合わせをじわじわと摺り寄せて行くんです。米国や豪州だと、州毎に認可制度が異なる。ひとえに無人機の認可と言っても、気が遠くなるような作業ですよね。また農薬の問題以外にも、クリアしなければいけない問題は多々あります」
現在、ヤマハ製の農薬散布用無人機は、日本国内で2700機が導入されており、全圃場(水田)の36%に散布を行っている。また、韓国で200機、オーストラリアで数十機が導入されているという。年間販売台数は300機ほどだが、今回米国で認可が下りたことから市場のさらなる拡大が期待されている。坂本氏はそのような現状も、30年以上にわたって培われてきたものだと話す。
「最初は事業として採算を考えられる次元ではありませんでした。そこから、無人小型ヘリを安全かつ効率よくビジネスとして成立させられる枠組みを、農林水産省と農林水産航空協会、そして我々の3者でひとつずつ作っていったんです。もちろん、JAや全農とも協力も不可欠でした。その積み重ねで現在に至っているというわけです」
これもあまり知られていない事実だが、海外で農薬散布に無人機を使っている国は、ヤマハが進出した地域だけだという。ヤマハ発動機は、競争相手がいない孤高な研究開発の道を一歩ずつ歩んできたことになる。
「実は、我々の会社では何か早くやり過ぎて失敗することも多いんです。無人機については、時代が受け入れはじめたので幸運だったとい言えるかもしれません」
そんなヤマハ発動機の経験は、日本のドローン産業の躍進にとって大きなマイルストーンになるのではないだろうか。そこで坂本氏に、ドローンの普及に必要な課題について聞いてみることした。

坂本氏がまず指摘したのは、飛行能力以外での技術力についてだった。
「農薬散布に限って言えば、機体の飛行性能以外にも、農薬散布のためのアプリケーションや機器の開発が進まなければいけません。重要度の割合で言うと、6対4でしょうか。それほど、農薬散布は難しい」
前述したが、農薬散布用無人機には防除効果や残留農薬の問題をクリアすることが求められる。撒き方にムラがあってもいけないし、撒き過ぎもまた問題となる。また、ただ撒けばよいという訳ではなく、しっかりと吹き付ける作業が必要になってくる。
ヤマハ発動機の無人機は、農作物の頭上3メートルから5メートルを飛行しつつ、メインローターから噴き出る風を使って吹き付けを行うそうだが、その部分を技術的に解消するのに多大な労力を要したそうだ。
「これは、農家にとっては非常に大きな問題なんです。お米は、地域の米を集めて、農協さんがライスセンターに納品し、残留農薬検査をするというプロセスを経ます。もしそこで一引っ掛かれば、何十トン、何百トンという米を廃棄しなければならない。そうなった場合、一体誰の責任なんだということになる。それを防ぐためにも、現場の声に耳を傾けながら技術を高めなければならないのです」
続けて、坂本氏はふたつ目の課題を指摘した。それは、無人機を使ったビジネス全体を動かす仕組みを考えなければならないということだ。
「技術革新が起きたとして、それを趣味の領域で使う分には何ら問題はありません。ただし、産業やビジネスとして成立させるためには、すべてパッケージで考える必要がある」
坂本氏がパッケージと表現したものは、社会的なインフラストラクチャーと言い換えることができる。ドローンについて言えば、性能認定や登録、点検・整備の仕組み、教習の制度、保険の問題などをセットで考えて行かなければならいという指摘である。
「また、その分野を職業とする人材を育てることも不可欠。農薬散布を例に挙げるならば、無人機を使用した防除を専門にやる人を職業として成り立たせてあげなければならない。他にも、整備する人、教習する人も、片手間にやらすわけにはいきません。技術習熟度が高い人的資源がなければ産業として成長が難しいし、リスクヘッジにも懸念が残る。これは、ビジネスモデルとしての課題でもあり我々も苦労しているところです」

ちなみに、ヤマハがFAAに認可を受ける際に決めてとなったのは、このパッケージだったという。
「FAAには、日本でひとつずつ精査していった点検整備マニュアルや、整備士を指導する要領などを英訳して提出している。教習ひとつとっても、まったく無人機を触ったことのない人が短時間で散布できるようになるために、技量なり知識を与える方法を模索しなければならない。そこが難しい点なんです。つまり、機体だけではなく、それを使う人材をどう教育、指導するかまで提示して、晴れて認可となった。ある意味、有人機の簡易版ですね。やはり、システム全体として提示しなければ認可は難しかったでしょう」
最後に、坂本氏にも今後の法整備の問題について意見を聞いてみた。
「いまちょうど規制の話が出ています。ドローンを実用化したい側は何でもできるって言いますし、リスクを懸念する側はとにかくダメという論調。噛み合っていない印象です。個人的には、社会が許容できる範囲を示すのが規制だと思うんですよ。車の制限速度で考えてみてください。本当に人にリスクがないスピードだと5~10㎞が精一杯。でも、それじゃあ、物流に支障をきたしますし、社会が成り立たない。そのために社会が許容できる線引きをするのが規制なんです。実際、ドローンについてはかなり厳しい規制でスタートすると個人的に想像しています。ただ、何もないよりいいこと。そこから、変えていけばいい。無人地帯しかだめなら、そこで実績を作って徐々に枠組みを変えていく。そういう作業を地道に続けなければ、産業としての発展はありえないと思う。一足飛びに、どこかのイベント会場で飛ばしたいという話になっちゃうと、世の中や技術も全くついてこない。まずはできることからはじめる。ヤマハ発動機も、関係省庁や日本産業用無人航空機協会など関係団と連携しながら、一歩ずつ歩を進めていこうと考えています」
技術の発展は問題意識を生み、問題意識は規制を生む。そしてさらなる技術の発展が規制を変え、人々の生活を豊かにする。ドローンはいま、ちょうどその入り口にいる。
「できることからはじめる」
無人飛行の分野で30年以上も技術とノウハウを蓄積してきたヤマハ発電機、そして坂本氏の言葉は重く、そして正しい。千里の道も一歩から。つまるところ、今も昔も世の中を変える方法にショートカットはないのかもしれない。
※同原稿は、扶桑社新書「ドローンの衝撃」に収録されたものを再構成したものです。